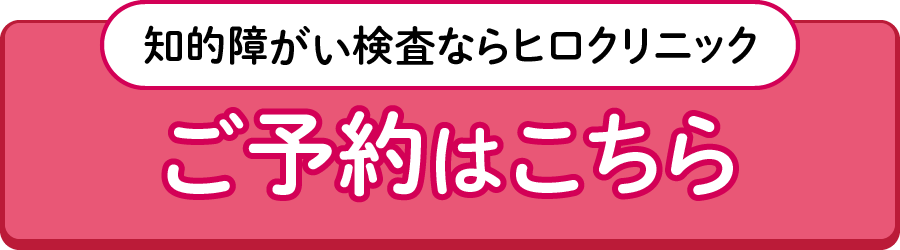小眼球症(Microphthalmia)および無眼球症(Anophthalmia)は、眼の発生異常により眼球が小さくなる、または完全に欠如する先天性疾患です。VSX2遺伝子の変異は、これらの疾患の主要な原因の一つであり、網膜前駆細胞の増殖や分化を制御する重要な役割を担っています。診断には眼科的評価と遺伝子検査が必要で、治療は義眼装着や手術による視覚機能の補助が中心となります。
遺伝子・疾患名
VSX2|Microphthalmia/Anophthalmia (VSX2-related)
概要 | Overview
小眼球症(Microphthalmia)および無眼球症(Anophthalmia)は、生まれつき眼の発育に異常が生じる先天性疾患であり、それぞれ眼のサイズが通常よりも小さい、または眼の構造が完全に欠如している状態を指します。VSX2(Visual System Homeobox 2)遺伝子は、眼の発生過程において極めて重要な転写因子をコードしており、その変異は常染色体劣性遺伝形式で小眼球症や無眼球症を引き起こすことが知られています。これらの疾患は、眼の形成異常として単独で発生する場合もあれば、コロボーマ(眼の構造の一部が欠損する状態)、白内障、虹彩異常などの合併症を伴うこともあります。VSX2は、網膜前駆細胞の増殖と分化を調節する役割を担っており、この遺伝子の機能不全は、発生過程における重要なシグナル経路を阻害し、重篤な眼形成異常を引き起こします。
疫学 | Epidemiology
小眼球症および無眼球症は、両者を合わせた発生率がおよそ出生1万人に1人と推定されています。これらの疾患は非常に遺伝的に多様性が高く、現在までに90種類以上の関連遺伝子が報告されています。VSX2遺伝子の変異は、小眼球症、無眼球症、コロボーマを含む「MAC(Microphthalmia, Anophthalmia, Coloboma)」症候群の約1.5%の症例に関与していると考えられています。小眼球症および無眼球症は、単独で発症する「非症候性(孤発性)」の場合と、他の先天異常を伴う「症候性」の場合があります。また、主な原因は遺伝的要因ですが、胎児期のウイルス感染、催奇形性を持つ薬剤の使用、母体の喫煙などの環境因子も発症リスクを高めるとされています。
病因 | Etiology
VSX2遺伝子は、網膜に特異的に発現する転写因子をコードしており、眼の発生において中心的な役割を担っています。この遺伝子は、網膜前駆細胞の増殖と分化を調節するとともに、代替的な細胞運命に関わる遺伝子の発現を抑制する働きを持っています。VSX2の病的変異(パソジェニックバリアント)は、この転写因子の機能を喪失させることで、網膜形成の異常を引き起こします。多くの病的変異はナンセンス変異媒介mRNA分解(Nonsense-Mediated Decay: NMD)を引き起こすか、DNA結合に必要なホメオドメインを欠損した機能不全タンパク質を生成することが知られています。これらの変異は、両眼性(両側性)の小眼球症やコロボーマと強く関連しており、白内障や錐体-杆体機能異常を伴う症例も報告されています。
症状 | Symptoms
VSX2関連小眼球症の症状は、個々の症例によって大きく異なり、軽度の眼サイズの縮小から、両眼の完全な欠如に至るまでさまざまです。また、以下のような眼の異常を伴うことがあります。
・コロボーマ(虹彩、網膜、脈絡膜の一部が欠損する先天異常) ・白内障(水晶体が濁り、視力低下を引き起こす病態) ・小角膜(角膜が通常よりも小さく、湾曲が強い状態) ・角膜混濁(角膜の透明性が失われる病態) ・網膜異形成(網膜の発達異常) ・眼裂狭小(瞼の開口部分が狭い状態)
また、一部の症例では、眼の異常に加えて発達遅延、ホルモン異常、難聴などの症状を伴うことがありますが、これらは比較的まれなケースとされています。
検査・診断 | Tests & Diagnosis
VSX2関連小眼球症の診断には、臨床的評価と遺伝学的検査の組み合わせが不可欠です。診断のために行われる主な検査には以下のようなものがあります。
まず、眼科的検査が行われます。細隙灯顕微鏡検査(スリットランプ検査)や眼底検査を用いて、眼の形態異常の有無を詳細に調べます。また、超音波検査を行い、眼球の大きさや内部構造を評価します。
さらに、磁気共鳴画像法(MRI)やコンピュータ断層撮影(CT)による画像診断が必要となることがあります。これらの検査によって、眼球の遺残組織の有無や、脳の形態異常の有無を確認することが可能です。
確定診断のためには、遺伝子検査が重要となります。全エクソームシーケンス(WES)やターゲットシーケンスを用いて、VSX2および関連遺伝子の病的変異を特定します。特に、両アレル(母親由来と父親由来の両方)にVSX2変異が認められた場合、診断が確定されます。
加えて、網膜の機能評価のために、網膜電図(ERG)が実施されることがあります。特に錐体-杆体機能障害が疑われる場合に有用です。
遺伝的背景が複雑な疾患であるため、分子診断の確定は、遺伝カウンセリングや再発リスクの評価、適切な管理計画を立てる上で極めて重要です。
治療法と管理 | Treatment & Management
VSX2関連小眼球症や無眼球症には根本的な治療法は存在せず、治療の目的は視覚機能の最大化と整容的な補助にあります。
特に、新生児期から義眼の装着や眼窩拡張器の使用を開始することにより、眼窩(眼球が収まる骨の空間)の正常な発育を促し、顔貌の非対称性を最小限に抑えることが推奨されます。
また、コロボーマの修復手術や白内障摘出手術、角膜移植などの外科的治療が、症例によっては検討されることがあります。
残存視力がある患者には、拡大鏡や電子機器を用いた視覚補助具、視覚リハビリテーションプログラム、特別支援教育の利用が推奨されます。
遺伝カウンセリングも非常に重要であり、遺伝形式や再発リスクについて適切な説明を受けることで、家族の今後の計画に役立ちます。
予後 | Prognosis
VSX2関連小眼球症や無眼球症の予後は、眼の発達異常の重症度によって異なります。片眼性の小眼球症で他の異常が少ない場合は、ある程度の視力を維持できる可能性がありますが、両眼性無眼球症の場合、視覚機能の回復は期待できません。しかし、早期から義眼装着や視覚補助が行われることで、審美的な改善や生活の質の向上が可能となります。
引用文献|References
- Basharat, R., Rodenburg, K., Rodríguez-Hidalgo, M., Jarral, A., Ullah, E., Corominas, J., Gilissen, C., Zehra, S. T., Hameed, U., Ansar, M., & De Bruijn, S. E. (2023). Combined single gene testing and genome sequencing as an effective diagnostic approach for anophthalmia and microphthalmia patients. Genes, 14(8), 1573. https://doi.org/10.3390/genes14081573
- Reis, L. M., Khan, A., Kariminejad, A., Ebadi, F., Tyler, R. C., & Semina, E. V. (2011). VSX2 mutations in autosomal recessive microphthalmia. Molecular vision, 17, 2527–2532.
- Napoli, F. R., Li, X., Hurtado, A. A., & Levine, E. M. (2024). Microphthalmia and Disrupted Retinal Development Due to a LacZ Knock-in/Knock-Out Allele at the Vsx2 Locus. Eye and Brain, 16, 115–131. https://doi.org/10.2147/EB.S480996
- Williamson, K. A., & FitzPatrick, D. R. (2014). The genetic architecture of microphthalmia, anophthalmia and coloboma. European Journal of Medical Genetics, 57(8), 369–380. https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2014.05.002
- Eintracht, J. (2023). Patient-specific stem cell-derived optic vesicles reveal novel pathogenic variants and common disease mechanisms in microphthalmia (Doctoral dissertation, UCL (University College London)).