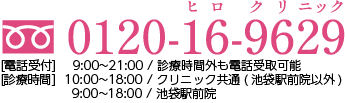赤ちゃんの性別はいつわかる?
赤ちゃんの性別は特別な検査を受けない場合、妊婦健診でおこなう超音波検査で判別します。男の子の場合は14~15週、女の子の場合は17~18週頃にわかる場合が多いですが、胎児の位置により見えづらかったりするともう少し遅れる場合もあります。
その他、羊水検査、絨毛検査、NIPT(新型出生前診断)などの出生前診断でも性別を判定することができます。これらの方法の場合、いつ頃性別を判定することができるのでしょうか。それぞれ解説します。

出生前に性別がわかる検査方法とその精度
出生前に性別を判別することができる検査には、超音波検査、羊水検査、絨毛検査、NIPT(新型出生前診断)があります。それぞれ詳しくみていきましょう。
超音波検査(エコー検査)
超音波検査(エコー検査)とは、母体に超音波を当てて、跳ね返ってきたデータから胎児の身体を映像化して性別を判別する方法です。この方法には2D、3D、4Dといった種類があります。
4Dは3Dに時間を加えたもので、より胎児の状態をリアルタイムで判別できるのが大きなポイントです。ただし、心臓の動きや身体の内部まで調べることはできません。
超音波検査は妊婦健診の際に行われます。その際に、胎児の外性器の画像から性別が判別できると、性別を教えてもらえることが多いでしょう。
男の子の場合は14~15週になると外性器が突起物として見えるようになります。女の子の場合は17~18週頃になると木の葉のような形をしている外性器が見えるようになります。場合によってはエコー写真で確認できることもあるでしょう。
ただし、胎児の位置や向きにより外性器が見えづらかったりすると、判定がもう少し遅れる場合もあります。
羊水検査
羊水検査は胎児や胎盤の正確な位置をあらかじめ超音波で確認した上で、お腹に細い針を刺して子宮から採取した羊水を調べ、染色体異常や性別を判別する検査です。
羊水検査は羊水の量によって左右されますが、基本的に妊娠16週~18週の間で検査を受けることができます。ほぼ100%の確率で胎児の性別が判別できることがポイントです。
絨毛検査
絨毛検査は、超音波画像に基づいてお腹に針を刺す方法か、あるいは腟内にカテーテルを入れる方法で、妊娠早期の胎盤の一部である絨毛を採取します。
採取した絨毛の検査をおこない、胎児の染色体を顕微鏡で確認して染色体異常や性別を検査します。染色体だけを検査するので全ての先天性疾患を判別することはできません。
絨毛検査は妊娠11週目~14週目で検査を受けることが可能であり、ほぼ100%の確率で胎児の性別を判別できることがポイントです。
羊水検査・絨毛検査のリスク
羊水検査は300分の1、絨毛検査は100分の1で流産・死産のリスクがあります。羊水検査や絨毛検査はほぼ100%の確率で性別を判別することができますが、リスクがあることが最大の問題といえるでしょう。
NIPT(新型出生前診断)
NIPT(新型出生前診断)とは、妊娠中の母親の血中に存在する胎児由来のDNA断片を採取して胎児の染色体異常を調べる検査をおこなうものです。
この検査は2013年から導入された検査方法で、母体からの採血のみという非常に少ない負担で子どもの染色体異常を調べることができることが最大の特徴です。非確定診断ではありますが、陰性的中率が非常に高く、偽陰性の確率が非常に低くなっています。
さらに非認証施設では、オプションとして性別判定を受けられる場合もあります。
NIPTでの性別判定は精度が高く、血液検査のみで実施できるため流産のリスクも伴いません。
また、妊娠6週目以降の早い時期から検査を受けることができるのも大きな特徴です。
NIPT(新型出生前診断)で性別がわかる理由
性別は性染色体の組み合わせで決まります。男の子ならXY染色体、女の子ならXX染色体の性染色体を持っています。NIPT(新型出生前診断)では、母親の血液から胎児由来のDNA断片を採取することにより、性染色体を調べることができるため、性別を判定することができるのです。
NIPT(新型出生前診断)の性別判定の精度
NIPT(新型出生前診断)では胎児由来のDNA断片を採取して検査をおこなうため、その精度は99.9%と非常に高い精度で判別することができます。

NIPT(新型出生前診断)で性別が外れることや間違いはある?
この検査を受ける上で注意しておきたいのは、あくまで99.9%で判別できることであって、性別が確実に分かる方法ではないということです。非常に安全な方法で、非常に早い時期から検査が受けられるとはいえ、0.1%の確率で予定していた性別が違う、外れたということが起こり得ます。
たとえばY染色体があることが判明した場合、99.9%の確率で男児の可能性が非常に高くなります。しかし、エコーではハッキリと確認できないこともありますし、非常に珍しいケースとして外性器の形成不全を起こしている可能性も考えられます。
必ずしも性別が100%判別できるというわけではないので、その点を踏まえた上で検査を受けるようにしましょう。
双子でもNIPT(新型出生前診断)は受けられる?
双子だと判明している場合でも受けられるのか気になるところですが、結論から言えば受けることが可能です。ただし、検査が受けられるのは双胎児の場合で、3人以上の時は判別できません。また、検査できるかどうかは施設によって左右されます。
もしも検査結果で陽性となった場合、一卵性双胎児だった時は双子のどちらも遺伝子の先天性異常の可能性があります。二卵性双胎児で陽性だった場合は双子のうち片方か、もしくは両方が先天性異常の可能性も否定できません。
NIPT(新型出生前診断)で双子の性別はわかる?
NIPT(新型出生前診断)では、性別をY染色体の有無で判断します。そのため、双子のケースでは、X染色体のみである場合は2人とも女の子であると判定ができますが、Y染色体が存在する場合は、2人とも男の子なのか、男の子女の子1人ずつなのかどうかは判別できません。
性別を教えてくれないことがあるって本当?
NIPT(新型出生前診断)は子どもの性別を判定することができますが、場合によっては性別を教えてくれないことがあります。というのも、日本産科婦人科学会は性別の告知を推奨していないからです。
そのためNIPTの認証(認定)施設では性別判定をおこなうことはできませんが、非認証施設では性別判定をおこなっている施設も多くあります。
なお、性別が分かるプランであっても性別を知りたくないという人のために、性別を知りたいかどうか自分で選択することも可能です。
まとめ
出産前に子どもの性別を知っておきたいかどうかは事前に夫婦で話し合っておくようにしましょう。事前に性別を知っていると、育児グッズの購入予定が立てやすいといったメリットがあります。一方で、出産時まで性別を知らない場合は、出産をしたときの驚きがより高まるかもしれません。
性別を早く知りたい方はNIPT(新型出生前診断)の受検はおすすめです。NIPTは高い確率で子どもの性別が判別できる上に、母体からの採血のみで検査をおこなうため流産や死産のリスクがなく、最も安全な出生前診断だと言えます。これまでの方法は安全におこなうことができても精度が低かったり、流産や死産になる可能性が少なからずあるといった問題がありました。
NIPTはそういった問題がないため、安全に、そしてより正確な出生前診断を受けたい妊婦さんにおすすめの検査です。年齢に関係なくどなたでも受検を検討することができます。出産する前に子どもの性別が知りたい方は、NIPTを検討してみてはいかがでしょうか。
Q&A
-
QNIPTで性別は何週目からわかりますか?妊娠6週目以降で検査が可能です。ただし、一般的には妊娠10週以降に検査を受けることが推奨されます。
-
QNIPTで性別の判定が99.9%という精度とはどういう意味ですか?胎児由来のDNAを解析するため、性染色体の組み合わせを非常に正確に判定できます。ただし、0.1%の誤差が存在します。
-
QNIPTの性別判定が間違う可能性はどのくらいありますか?99.9%の精度が示す通り、間違いは非常に稀ですが、0.1%程度の確率で誤判定が起こる可能性があります。
-
QNIPTで性別を判定する方法はどのようなものですか?母体の血液に含まれる胎児由来DNAから性染色体(X染色体またはY染色体)を解析することで性別を判定します。
-
Q双子の場合、NIPTで性別はどう判定されますか?Y染色体の有無を調べることで、少なくとも1人が男児かどうかを判定しますが、詳細な個別の性別判定はできません。
-
QNIPTの性別判定は流産リスクがありますか?いいえ、NIPTは母体から採血するだけの非侵襲的検査であり、流産リスクはありません。
-
QNIPTで性別を知りたくない場合はどうすればよいですか?検査前に医療機関に性別を教えないよう依頼することが可能です。
-
QNIPTの性別判定結果はどのくらいの期間でわかりますか?検査から結果が出るまで1~2週間程度かかることが一般的です。
-
QNIPTはどの施設でも性別判定をしてくれますか?日本産科婦人科学会認証施設では性別判定を行わない場合がありますが、非認証施設では性別判定を提供しているところもあります。
-
QNIPTの性別判定に追加料金がかかりますか?施設によって異なりますが、性別判定をオプションとしている場合、追加料金が発生することがあります。
-
Q性別判定以外にNIPTで何がわかりますか?主に21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー(エドワーズ症候群)、13トリソミーなどの染色体異常を調べることができます。
-
Q妊娠6週目でも正確に性別が判定されますか?検査の精度は高いものの、胎児由来DNAの濃度が低い場合、再検査が必要になることがあります。
-
QNIPTで判定された性別が超音波検査と異なる場合はどうしたらよいですか?最終的な確認は出生後になりますが、場合によっては他の検査方法で確認することも可能です。
-
QNIPTを受ける条件や制限はありますか?日本では年齢や妊娠経過に関わらず検査を受けられる施設もありますが、施設ごとに条件が異なる場合があります。
-
QNIPTの性別判定を事前に受けるメリットは何ですか?育児用品の準備がしやすくなるほか、出産後の生活設計が立てやすくなります。
-
Q性別判定のためだけにNIPTを受けるのは可能ですか?一部の非認証施設では可能ですが、通常は染色体異常検査を目的とした検査の一部として提供されます。
-
QNIPTの性別判定結果に満足できない場合、他の方法を試すべきですか?正確性は高いですが、完全ではありません。他の方法として羊水検査や絨毛検査を検討することも可能です。
-
Q性別判定結果が間違っているケースの原因は何ですか?胎児由来DNAの濃度不足や母体由来のDNAの混入が原因となる場合があります。
-
QNIPTで性別を判定する際、医師の許可は必要ですか?施設の方針や医師の判断により、事前説明や同意が求められる場合があります。
-
QNIPTと他の性別判定方法の違いは何ですか?NIPTは非侵襲的で早期から検査が可能であり、精度も高い点が特徴です。一方、羊水検査や絨毛検査はリスクが伴いますが、100%近い精度が得られます。
記事の監修者

岡 博史先生
NIPT専門クリニック 医学博士
慶應義塾大学 医学部 卒業

 中文
中文