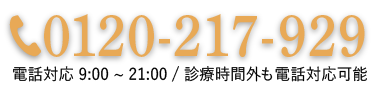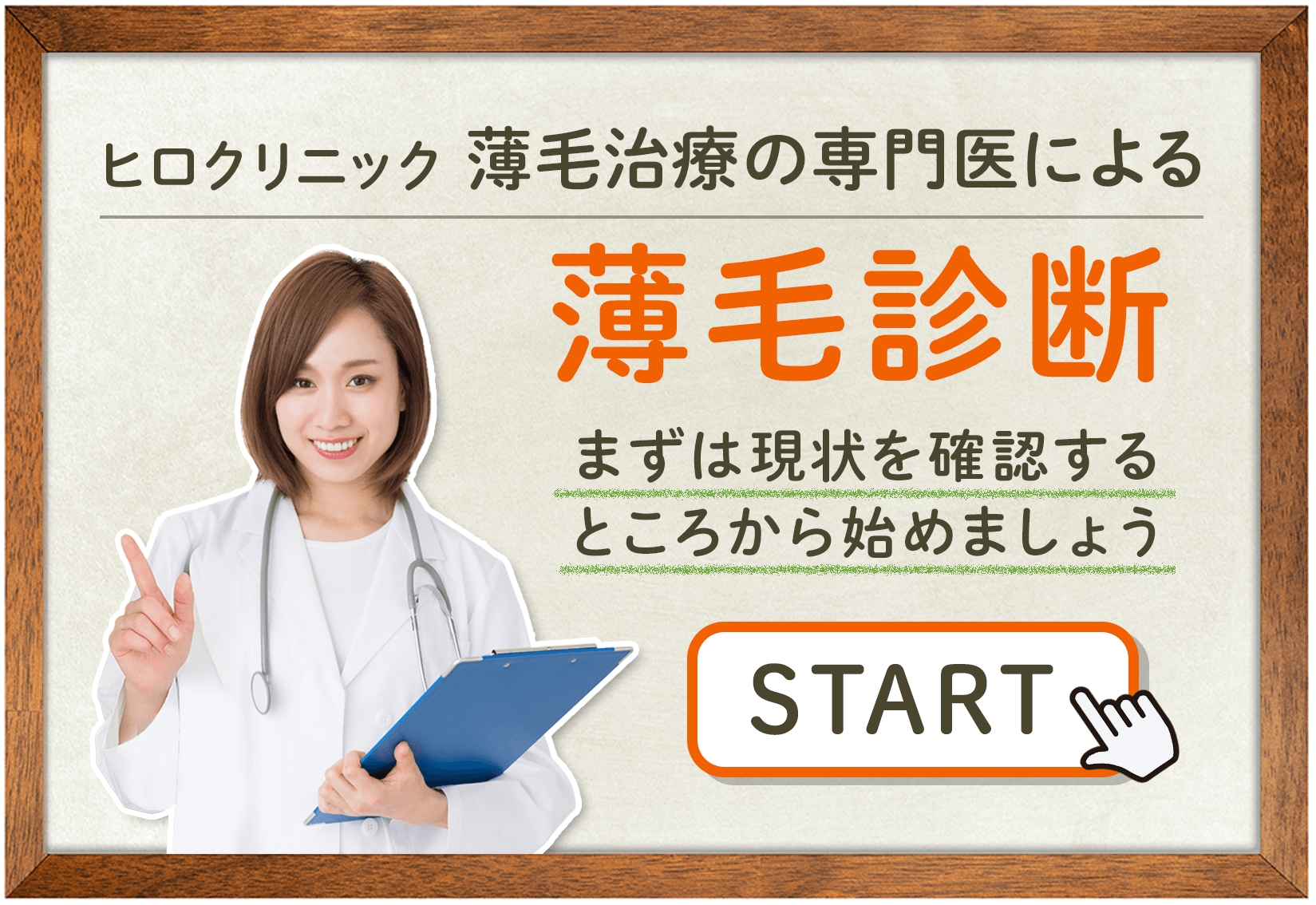日々の食事や生活習慣が、髪の元気や肌の若々しさにまで影響するかもしれないと聞いたら驚くでしょうか?実は「肥満」が、体の中で再生や修復を担う「幹細胞」の働きを弱めることで、髪が細くなったり、見た目だけでなく実際に老けやすくなることが研究で示されています。本記事では、研究の根拠をもとに、肥満と髪や肌の変化の関係をわかりやすく解説します。
肥満は幹細胞を通じて組織の再生力に影響を与える可能性がある
世界中で肥満が深刻な健康問題として注目されています。肥満は、2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus)、心血管疾患(cardiovascular disease)、高血圧(hypertension)などの代謝性疾患と強く関連しているだけでなく、老化の加速や、さまざまな臓器における組織機能の低下とも関係していることがわかってきました。これまでの疫学的(多くの人を対象とした統計的な研究)や臨床的な研究により、肥満と健康問題の関係は明らかになりつつありますが、なぜ過剰な脂肪が細胞レベルで組織の安定性(恒常性)を壊すのか、その正確な仕組みについては、まだ解明されていない点が多く残されています。
特に注目されているのは、肥満が身体の中にある「成体幹細胞(adult stem cells)」に与える影響です。これらの幹細胞は、傷ついた組織を修復したり、古くなった細胞を新しく入れ替えたりする重要な役割を担っています。そのため、幹細胞の機能が落ちると、臓器全体の再生力が下がってしまうのです。

髪の根元にある「毛包」とは? そこにある幹細胞はどんな働きをしているの?
老化や肥満の影響を受けやすい「ミニ臓器」の代表が、毛の根元にある「毛包(もうほう/hair follicle)」です。毛包は、髪の毛の生え変わりを支える非常にダイナミックな構造を持っており、一生の間に「退行期(catagen)」「休止期(telogen)」「成長期(anagen)」という3つの周期を繰り返しています。
このうち、実際に髪が伸びるのは「成長期(anagen)」であり、この時期に特に重要な役割を果たしているのが「毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)」です。

HFSCsは、毛包の中にある「バルジ領域(bulge region)」と呼ばれる特定の場所に存在しています。通常は眠っているような「静止状態(quiescent state)」にありますが、成長期が始まると活性化し、さまざまな細胞に変化(分化)して新しい髪をつくり出します。
HFSCsには、大きく3つの特徴があります。
1つ目は、長期間にわたって静止状態を保てること、
2つ目は、活性化すると急速に細胞を増やせること(増殖性が高いこと)、
そして3つ目は、必要に応じて複数の種類の細胞に分化できる柔軟性(多分化能)を持っていることです。
これらの性質のおかげで、HFSCsは毛の再生を長く支えることができるのです。

年齢とともに弱まる幹細胞の力と髪の変化

年を重ねると、毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)の数が少なくなったり、働きが弱まったりすることで、髪にさまざまな変化が現れます。たとえば、髪が細くなる、伸びるスピードが遅くなる、毛包(hair follicle)そのものが小さく縮んでしまう「ミニチュア化(miniaturization)」といった現象が見られるようになります。
こうした加齢にともなう変化には、HFSCsを正しい場所にとどめて機能を保つ役割をもつあるタンパク質が関わっています。それが「コラーゲン17型α1鎖(collagen type XVII alpha 1 chain:COL17A1、別名コラーゲンXVII)」です。
COL17A1は、HFSCsを毛包の基底膜(basement membrane)にしっかりと固定する働きをしています。しかしこのタンパク質が失われると、HFSCsは毛包内で位置を維持できなくなり、早い段階で機能を失ってしまう(枯渇する)ことが、動物実験によって明らかにされています。

肥満が原因で髪が抜ける?その仕組みに迫る
肥満は、男性型や女性型の脱毛症(androgenic alopecia:AGA)といったホルモンに関係する脱毛と関連があることが知られています。しかし、これまでの研究では、ホルモン以外に肥満が毛包(hair follicle)全体にどのような影響を及ぼすのかは、あまり詳しくわかっていませんでした。
そこで研究者たちは、肥満と毛の関係を明らかにするため、マウスを用いた実験を行いました。高齢のオスのマウス(人間で言えば60〜70歳に相当)に対し、1か月間にわたり「高脂肪食(high-fat diet:HFD)」または「標準食(normal diet:ND)」を与えて、その変化を観察しました。実験を始めた時点では、どちらのマウスにも目立った脱毛は見られませんでした。

ところが、わずか1か月後、HFDを与えられたマウスでは、目に見えるほど広範囲に毛が抜けていました。一方、NDを食べていたマウスでは毛の状態に変化はなく、正常に保たれていました。
さらに、血糖値が高いことで知られる糖尿病モデルマウス(レプチン受容体が機能しないdb/dbマウス)や、高糖分の食事を与えられたマウスでは、このような脱毛は起きませんでした。これにより、今回見られた脱毛は、血糖値の高さやインスリンの働きに問題があるからではなく、肥満にともなう「脂質の過剰(lipid overload)」が主な原因である可能性が高いと考えられました。
また、先天的に「レプチン(leptin)」というホルモンが作られず、生まれつき太りやすいob/obマウスでも、同様に毛包の構造が劣化していることが確認されました。

毛包の構造変化と幹細胞の異常なふるまい
顕微鏡を使って高脂肪食(high-fat diet:HFD)を与えたマウスの皮膚組織を詳しく観察したところ、毛包(hair follicle)に大きな構造的な異常が見られました。特に、毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)が存在する「バルジ領域(bulge region)」が失われている毛包が多く確認されました。
さらに、通常は髪や皮膚を油分で保護するための「皮脂腺(sebaceous gland)」が、異常に大きく残っているケースが多く見られました。これは、本来なら髪の再生に使われるべきHFSCsが、誤って皮脂腺の細胞に変わってしまった可能性、つまり「異常分化(aberrant differentiation)」が起きていたことを示しています。

このような変化は、オス・メス両方のマウスに共通して見られ、体重が重いマウスほど症状が強くなるという関連も確認されました。
また、マウスの毛には3種類あり、太くて硬い「ガードヘア(guard hair)」、中くらいの太さの「アウル・オウシーンヘア(awl/auchene hair)」、そして最も細い「ジグザグヘア(zigzag hair)」があります。HFDを与えられたマウスでは、特にこの細いジグザグヘアが抜けやすくなっていました。これは、こうした小さな毛をつくるHFSCsに、より強い再生負担がかかっている可能性を示唆しています。
さらに、HFDマウスでは、皮膚の「真皮(dermis)」と呼ばれる中間層が薄くなっていた一方で、その下にある「皮下組織(subcutaneous tissue)」、つまり脂肪層が厚くなっていました。これは、加齢によって起きる皮膚の変化と似た傾向です。
一方で、皮膚の一番外側にあたる「表皮(epidermis)」の厚さには大きな変化がなかったため、表皮幹細胞(epidermal stem cells)は、HFSCsに比べて代謝ストレスに対してより強い性質を持っていると考えられます。

肥満が髪の生え変わりのリズムと幹細胞の目覚めるタイミングを乱す
肥満が毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)に与える影響として、特に重要な発見の一つが、毛の生え変わりの周期、いわゆる「毛周期(hair cycle)」の乱れです。高脂肪食(high-fat diet:HFD)を与えられたマウスでは、毛周期に異常が起きていることが明らかになりました。
具体的には、髪の毛が成長する「成長期(anagen)」の期間が短くなり、通常よりも早く「休止期(telogen)」に移行してしまっていたのです。つまり、髪が十分に伸びる前に、成長が止まってしまうという異常なリズムが起こっていました。

この変化は、HFSCsが活性化するタイミングや、毛包内の「微小環境(microenvironment)」が肥満によって変化してしまったことを示しています。とくに注目されたのは、「真皮(dermis)」と呼ばれる皮膚の中間層に脂肪が増える「皮膚内の脂肪蓄積(dermal adiposity)」が関係していた点です。
驚くべきことに、こうした大きな変化が起きていたにもかかわらず、炎症細胞の侵入(免疫細胞の浸潤)、毛細血管の減少、神経の損傷といった通常みられる組織の傷みは確認されませんでした。
つまり、肥満の影響は、炎症や血流の悪化といった周辺環境の変化によるものではなく、HFSCsそのものが主な標的となっていたことが明らかになったのです。

幹細胞はなぜ毛をつくらず、皮膚に変わってしまうのか?
幹細胞(stem cells)が肥満の影響を受けてどのように振る舞うのかを詳しく調べるために、研究者たちは特殊な遺伝子改変マウスを使って実験を行いました。このマウスでは、毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)とその子孫の細胞に蛍光ラベルをつけて、体内での動きを追跡できるようになっています。
通常の食事を与えたマウスでは、HFSCsは毛包の「バルジ領域(bulge region)」にとどまり、髪が伸びる「成長期(anagen)」になると、毛の根元方向(下向き)に分化し、新しい髪をつくっていました。
ところが、高脂肪食(high-fat diet:HFD)を3か月間与えたマウスでは、バルジ領域からHFSCsが失われ、代わりにその子孫細胞が毛包の上部、たとえば皮脂腺(sebaceous gland)や接合部領域(junctional zone)、毛包の外側にある表皮(epidermis)へと移動していました。これは、老化や皮膚のダメージがある場合によく見られる現象と似ていました。

このように、本来は髪の再生を担うはずの幹細胞が、全く別の種類の細胞になってしまう現象は、「幹細胞の運命転換(fate-switching)」と呼ばれています。つまり、HFSCsが髪をつくるのではなく、皮膚の表面を構成する「表皮細胞(epidermal cells)」になってしまうのです。
実際に、この運命転換が起きた細胞では、皮膚に特有のマーカーである「ケラチン1(keratin 1:K1)」などが発現しており、本来の毛を構成する性質を失い、皮膚としての特徴を持つようになっていました。
さらに興味深いことに、毛を引き抜くといった物理的または化学的な刺激(脱毛処理、depilation)を加えるだけでも、HFDマウスでは同じように運命転換が起きてしまいました。本来であれば、こうした刺激は幹細胞を目覚めさせ、髪の再生を促すはずです。しかし、肥満による代謝ストレスが加わることで、逆に幹細胞のはたらきを乱し、本来とは異なる細胞へと変わってしまう。望ましくない逆効果が起こっていたのです。

なぜ幹細胞は誤って皮膚になってしまうのか? その分子レベルの仕組みとは
幹細胞(stem cells)が本来の役割を離れ、髪をつくらずに皮膚の細胞へと変化してしまう「運命転換(fate-switching)」は、なぜ起きたのでしょうか? この疑問に答えるために、研究者たちは2つの分子解析技術を用いて、そのメカニズムを詳しく調べました。
1つ目は「RNAシーケンシング(RNA sequencing)」という手法で、細胞の中で実際にどの遺伝子が働いているのかを読み取ることができます。2つ目は「ATAC-seq(Assay for Transposase-Accessible Chromatin using sequencing)」と呼ばれる方法で、DNAがどの程度開かれているか、つまり、どの遺伝子が使いやすい状態になっているかを解析する技術です。

これらの技術を用いて、加齢によって自然に老化したマウスと、高脂肪食(high-fat diet:HFD)を与えたマウスを比較したところ、興味深い違いが明らかになりました。
加齢による老化では、加齢のマーカーとされる「Col17a1(collagen type XVII alpha 1 chain)」の発現が大きく低下していました。一方、HFDマウスの毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)では、加齢では見られないタイプの変化が観察されました。それは「エピジェネティックな変化(epigenetic changes)」と呼ばれるもので、DNAの配列そのものには変化がないものの、遺伝子の発現のされ方が変わってしまっていたのです。
とくに注目されたのは、HFSCsが静止状態(quiescence)を維持するために必要な転写因子である「NFATC1(nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 1)」と「MED1(mediator complex subunit 1)」が作用するDNA領域の構造が閉じ気味になっていたことです。これは、幹細胞が本来のように“眠っている”ことができず、早く目覚めすぎてしまう可能性があることを示しています。
幹細胞が必要以上に早く活性化されると、その分だけ働きすぎて早く消耗し、髪の再生能力が長く持たなくなる。このリスクが肥満によって高まっていると考えられるのです。

幹細胞の働きを止める原因は?重要なシグナル伝達経路の抑制とは
肥満が毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)に与える影響として、もう一つ注目すべき点があります。それは、幹細胞の機能を支える「シグナル伝達経路(signaling pathways)」が、高脂肪食(high-fat diet:HFD)を与えられたマウスでは大きく抑制されていたということです。
特に影響を受けていたのは、「MAPK経路(mitogen-activated protein kinase pathway)」と「SHH経路(Sonic Hedgehog pathway)」という2つの重要な経路です。
このうち、SHH経路(Sonic Hedgehog pathway)は、胎児の発生や成体の組織再生に深く関与しており、毛包(hair follicle)においては「成長期(anagen)」への移行を誘導する鍵となる経路です。この経路が正常に働かないと、HFSCsは活性化されず、髪が伸びるための準備が整わなくなってしまいます。

実際、SHH経路の働きを選択的に遮断できる遺伝子改変マウスを使った実験でも、その重要性が明らかになりました。研究では、たった1週間SHHの機能を止めただけで、HFSCsが毛包から失われ、毛包自体が小さくなって(ミニチュア化し)、目に見える脱毛が引き起こされました。
この結果は、HFDを与えられたマウスで観察された変化とほぼ同じであり、肥満によってSHH経路が抑制されることが、幹細胞機能の低下と脱毛の直接的な原因である可能性が高いことを示しています。

なぜSHH経路は肥満で止まってしまうのか? 炎症と酸化ストレスの関係
それでは、なぜ高脂肪食(high-fat diet:HFD)を摂ることで、Sonic Hedgehog(SHH)経路の働きが抑えられてしまうのでしょうか? その理由を探るために、研究者たちはSHH経路の「上流」にあたる炎症シグナルに注目しました。
特に注目されたのが、「インターロイキン1受容体(interleukin-1 receptor:IL-1R)」を介する経路です。この経路は、炎症性サイトカインの一種である「インターロイキン1ベータ(interleukin-1 beta:IL-1β)」によって活性化されます。IL-1βは、細胞の中にある転写因子「NF-κB(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells)」を刺激し、炎症反応を引き起こす働きを持っています。

HFDを与えられたマウスでは、皮膚の表皮や毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)でIL-1βの発現が高まっており、同時に「8-オキソグアニン(8-oxoguanine)」という酸化ストレスの指標も増加していました。これは、活性酸素種(reactive oxygen species:ROS)によってDNAが傷ついた痕跡です。
さらに、HFSCsの内部には「脂肪滴(lipid droplets)」が蓄積しており、これは脂肪の過剰による細胞障害、いわゆる「リポトキシシティ(lipotoxicity)」が起きていることを示していました。
では、これらの炎症や酸化ストレスがSHH経路にどのような影響を与えているのでしょうか?
研究者たちは、皮膚の角化細胞(keratinocyte)を用いた培養実験を行いました。これらの細胞にIL-1β、もう一つの炎症性サイトカインであるIL-6、そして活性酸素(ROS)を加えると、SHH経路の標的遺伝子であるGli1、Gli2、Ptch1の発現が大きく抑制されることが確認されました。
一方で、炎症性サイトカインの一種であるTNF(腫瘍壊死因子、tumor necrosis factor)を加えても、このような抑制は見られませんでした。つまり、炎症が起きれば何でもSHH経路を止めるというわけではなく、特定の因子(IL-1βやIL-6、ROSなど)が関与していることが示されました。
さらに、マウスの皮膚にIL-1βを直接注射するという実験も行われました。その結果、SHH経路の活動が実際に抑えられました。ただし、若いマウスの皮膚では炎症反応のマーカーである「COX2(cyclooxygenase-2)」には大きな変化が見られず、若い皮膚には一時的な炎症ストレスに対するある程度の耐性があることもわかりました。

炎症がずっと続くと、髪はどうなる? IL-1シグナルの慢性活性化と脱毛の関係
炎症がずっと続くと、毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)はどのような影響を受けるのでしょうか? この疑問に答えるために、研究者たちは「IL-1受容体拮抗因子(interleukin-1 receptor antagonist:IL-1Ra)」という、炎症を抑える分子が働かないように遺伝子操作されたマウスを用いて実験を行いました。このマウスは「IL-1Raノックアウトマウス(IL-1Ra knockout mice)」と呼ばれます。
このマウスでは、体内のIL-1経路(interleukin-1 signaling pathway)が常に活性化された状態にあります。つまり、特別な外的炎症や感染症がなくても、体の中では慢性的な炎症のシグナルが出続けている状態です。
その結果、IL-1Raノックアウトマウスでは、部分的な脱毛が見られました。これは、全身に強い炎症が起きていなくても、IL-1のシグナルが長期間にわたって継続的に活性化されることで、HFSCsの働きが妨げられ、髪の再生がうまくいかなくなる可能性があることを示しています。

IL-1βはどこから来るのか? 実は免疫細胞ではなかった
一般的に、IL-1β(interleukin-1 beta)のような炎症性サイトカイン(inflammatory cytokine)は、Tリンパ球などの免疫細胞(immune cells)によって分泌されると考えられています。しかし、高脂肪食(high-fat diet:HFD)を与えられたマウスでは、事情が少し異なっていました。
今回の研究により明らかになったのは、IL-1βの主な発生源が、毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)自身、あるいはその周囲にある皮膚の細胞(skin cells)であるということです。
つまり、免疫細胞が外から炎症を起こしていたのではなく、皮膚の中の細胞が自らの「代謝ストレス(metabolic stress)」によってIL-1βを生み出し、皮膚の内部で炎症を自己増幅させる「ループ」ができていたのです。
この発見は、炎症が必ずしも外的な免疫反応から始まるわけではなく、肥満により細胞自身がストレスを感じた結果として、皮膚内で慢性的な炎症状態が作り出されてしまう可能性を示しています。

炎症より先に起こるのは? 幹細胞を揺るがす酸化ストレスの影響とは
高脂肪食(high-fat diet:HFD)を始めてからわずか4日間で、毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)にどのような変化が起きるのかを調べたところ、非常に早い段階で「ミトコンドリア由来の活性酸素(mitochondrial reactive oxygen species:mitochondrial ROS)」の増加が確認されました。
一方で、この時点ではまだ、「Sonic Hedgehog(SHH)経路」や「NF-κB(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells)経路」、「インターロイキン1受容体経路(interleukin-1 receptor:IL-1R pathway)」など、炎症に関わるシグナル伝達経路には大きな変化は見られませんでした。
この結果から、HFDによる影響はまず酸化ストレス(oxidative stress)として現れ、それが幹細胞の働きを乱す最初の引き金になっている可能性が高いと考えられます。
さらに実験では、代表的な活性酸素の一種である「過酸化水素(hydrogen peroxide)」を皮膚に塗布するだけでも、HFSCsが本来の毛包幹細胞としてのふるまいをやめてしまい、「表皮細胞(epidermal cells)」へと分化してしまう現象が確認されました。
つまり、炎症が始まるよりも前に、酸化ストレスだけで幹細胞の「アイデンティティ」や運命を大きく変えてしまう力があるということが、明確に示されたのです。

脱毛を防ぐにはどうすればいい? 効果的な介入法とは
高脂肪食(high-fat diet:HFD)によって引き起こされる脱毛を防いだり、元の状態に戻したりする方法についても、さまざまな実験が行われました。
まず試されたのは、抗酸化剤(antioxidants)の投与、IL-1シグナル(interleukin-1 signaling)を抑えるための遺伝子操作、そして幹細胞の安定に関わるタンパク質「COL17A1(collagen type XVII alpha 1 chain)」を強制的に発現させる方法です。しかし、これらの手法では、毛の正常な再生を取り戻すことはできませんでした。
一方で、毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)の活性に深く関わる「Sonic Hedgehog経路(Sonic Hedgehog pathway:SHH経路)」に注目した介入では、改善が見られました。具体的には、SHH経路を遺伝的に活性化したり、「SAG(Smoothened agonist)」というSHH経路を刺激する物質を使用することで、HFDマウスにおいてHFSCsの機能が部分的に回復し、毛の再生が促されました。
ただし、これらの効果はHFDによる脱毛に限られたものであり、加齢によって自然に起こるHFSCsの機能低下には効果がありませんでした。つまり、SHH経路の働きが低下するという弱点は、肥満に特有の現象であり、加齢とは異なる仕組みであることが示されたのです。

肥満は本当に老化を早めるのか? 幹細胞から見えてきた新たな可能性
高脂肪食(high-fat diet:HFD)の影響が時間とともにどのように蓄積されるのかを調べるために、研究者たちは複数の毛周期(hair cycle)にわたってマウスの毛包幹細胞(hair follicle stem cells:HFSCs)の状態を観察しました。
その結果、HFDを与えられたマウスでは、毛周期が繰り返されるごとにHFSCsへのダメージが徐々に蓄積していくことが確認されました。この「累積的な損傷(cumulative damage)」は、肥満が単なる脱毛の原因になるだけではなく、再生能力の低下や老化の進行を早める「増幅因子(amplifier)」として働く可能性を示しています。

このような結果は、「幹細胞の疲弊(exhaustion)」「誤った分化(misdifferentiation)」「消失(depletion)」といった細胞レベルの変化が、組織の老化を引き起こすという、新しい「幹細胞中心の老化理論(stem cell–centric theory of aging)」を強く支持するものです。
今回の研究はマウスを対象としたものですが、もし同様の仕組みが人間の皮膚や髪にも当てはまるのであれば、肥満は見た目の老化や脱毛の進行を加速させる重要な要因になり得ます。
つまり、私たちが日々の食生活や生活習慣を見直すことは、糖尿病や心血管疾患といった代謝性疾患を予防するためだけでなく、幹細胞の力を守り、髪や肌の若々しさを保つためにも大切だと考えられるのです。

キーワード
肥満, 幹細胞, 毛包, 毛包幹細胞, 再生力, 高脂肪食, 脱毛, 毛周期, コラーゲン17型, IL-1β, 酸化ストレス, NF-κB, Sonic Hedgehog経路, SHH経路, 運命転換, 異常分化, 表皮幹細胞, リポトキシシティ, 脂肪滴, 加齢

引用文献
- Morinaga, H., Mohri, Y., Grachtchouk, M. et al. Obesity accelerates hair thinning by stem cell-centric converging mechanisms. Nature 595, 266–271 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03624-x
- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature 596, 583–589 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2
- Mihaly Varadi, Damian Bertoni, Paulyna Magana, Urmila Paramval, Ivanna Pidruchna, Malarvizhi Radhakrishnan, Maxim Tsenkov, Sreenath Nair, Milot Mirdita, Jingi Yeo, Oleg Kovalevskiy, Kathryn Tunyasuvunakool, Agata Laydon, Augustin Žídek, Hamish Tomlinson, Dhavanthi Hariharan, Josh Abrahamson, Tim Green, John Jumper, Ewan Birney, Martin Steinegger, Demis Hassabis, Sameer Velankar, AlphaFold Protein Structure Database in 2024: providing structure coverage for over 214 million protein sequences, Nucleic Acids Research, Volume 52, Issue D1, 5 January 2024, Pages D368–D375, https://doi.org/10.1093/nar/gkad1011
- Perez, G., Barber, G. P., Benet-Pages, A., Casper, J., Clawson, H., Diekhans, M., Fischer, C., Gonzalez, J. N., Hinrichs, A. S., Lee, C. M., Nassar, L. R., Raney, B. J., Speir, M. L., van Baren, M. J., Vaske, C. J., Haussler, D., Kent, W. J., & Haeussler, M. (2025). The UCSC Genome Browser database: 2025 update. Nucleic acids research, 53(D1), D1243–D1249. https://doi.org/10.1093/nar/gkae974
- Wang, X., Liu, Y., He, J., Wang, J., Chen, X., & Yang, R. (2022). Regulation of signaling pathways in hair follicle stem cells. Burns & Trauma, 10, tkac022. https://doi.org/10.1093/burnst/tkac022
- Oh, J., Lee, Y. D., & Wagers, A. J. (2014). Stem cell aging: mechanisms, regulators and therapeutic opportunities. Nature medicine, 20(8), 870–880. https://doi.org/10.1038/nm.3651