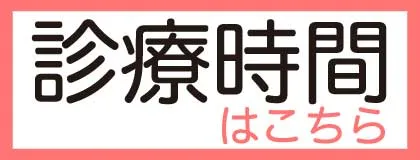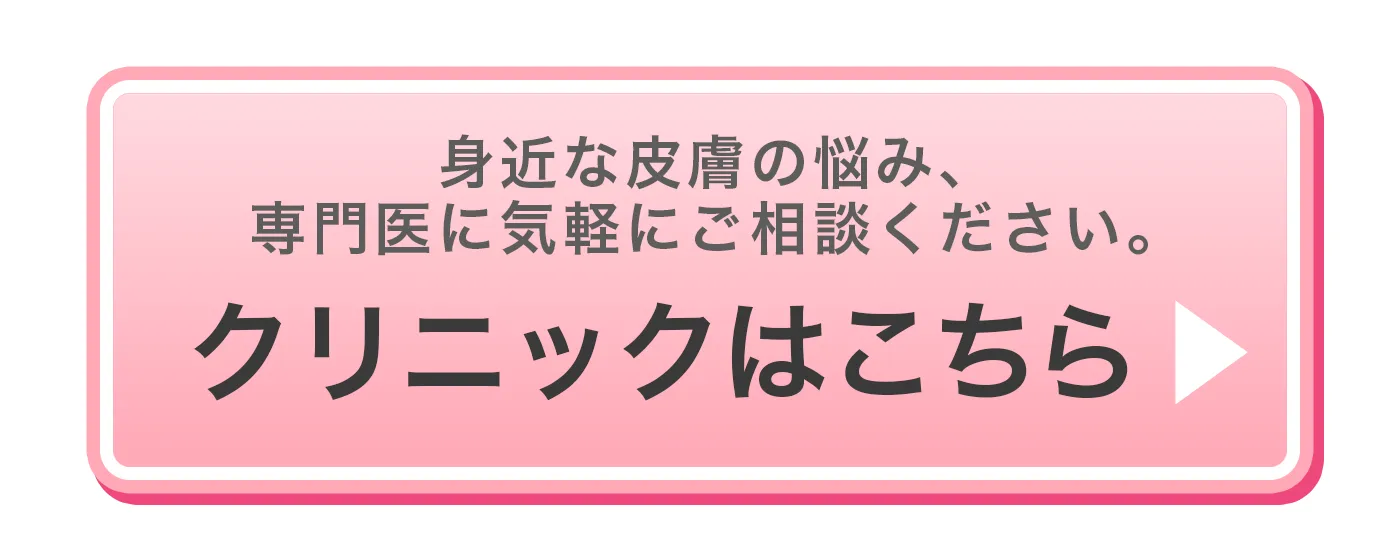人種や地域による顔の老化の違い
白人女性と日本人女性におけるシワとたるみの比較
2004年にTsukaharaらが行った研究では、アメリカ・オハイオ州シンシナティに住む健康な白人女性85名と、日本・東京に住む健康な日本人女性70名(いずれも20〜69歳)を対象に、顔のシワおよびたるみの年齢変化を比較しました。評価は、正面および斜め45度から撮影した標準化された顔写真を用いて行われ、全員のシワとたるみを同一の熟練した評価者が採点することで、主観の影響を最小限に抑えています。
顔のシワは、額(forehead)、眉間(glabella)、上まぶた(upper eyelid)、目尻(outer eye corner, 通称crow’s feet)、下まぶた(lower eyelid)、頬(cheek)、鼻唇溝(nasolabial groove)、口角(corner of the mouth)の8部位にわたって評価されました。これらの部位は、顔の表情に関わる筋肉や皮膚の構造が異なるため、部位ごとの加齢変化の傾向を詳細に把握することが可能になります。

結果として、両グループともすべての部位でシワのスコアは加齢に伴って上昇していましたが、20〜29歳の若年層では白人女性の方が有意に高いシワスコアを示しました。つまり、白人女性では比較的若い段階からシワの形成が始まる傾向があることが明らかになりました。
また、年齢が進むにつれて額や眉間、上まぶた、目尻などの“顔の上部”に関しては、両グループのシワスコアはほぼ同じになっていきました。一方、“顔の下部”にあたる下まぶた、頬、鼻唇溝、口角のシワに関しては、全ての年齢層において白人女性の方が日本人女性より顕著に高いスコアを示し、その差は年齢とともにさらに拡大する傾向が見られました。

加えて、頬骨下部(subzygomatic area)における皮膚のたるみスコアも年齢とともに上昇しており、特に40歳以上の年齢層では白人女性のスコアが有意に高いことが確認されました。これらの結果は、白人女性が日本人女性に比べて顔の下部における皮膚のたるみに対して感受性が高く、その影響でシワもより顕著に現れる可能性を示しています。
皮膚のたるみは、皮膚の弾力性の低下、真皮(皮膚の中層)に含まれるコラーゲンやエラスチンといった構造タンパク質の変性、重力の影響などが複雑に関係して生じる現象です。したがって、顔の下部のシワが目立ちやすいというのは、単なる表皮の変化だけでなく、深層構造の変化や顔全体の解剖学的特性も影響していると考えられます。

アジア女性における顔の老化の都市間比較:日本、中国、タイ
Tsukaharaらは2007年に、さらに研究の対象を広げ、東京(日本)、上海(中国)、バンコク(タイ)に居住するアジア人女性277名を対象に、顔のシワと頬のたるみの加齢変化を比較しました。対象年齢は10代から60代まで幅広く、年齢ごとに年代別の傾向を詳細に把握することが目的です。
顔のシワは前述と同様に8部位で評価され、頬のたるみは日本人女性の写真をもとに開発された6段階スケールで評価されました。全ての写真は正面および斜位から標準化された条件下で撮影され、1名の評価者によって一貫して採点されました。

結果として、すべての都市のすべての顔部位において、年齢とともにシワのスコアが上昇する明確な相関が見られました(相関係数r = 0.799〜0.931、p < 0.01)。特に、バンコクのタイ人女性が最も深いシワを有しており、次に中国人女性、そして最も少なかったのが日本人女性という順序でした。
この傾向は、顔の下部(頬、鼻唇溝、口角)で特に顕著であり、タイ人女性は20代から50代にかけて明確に他のグループより深いシワを示しました。中国人女性は、眉間や目尻などの“目の周囲”において、日本人女性よりもシワのスコアが高い傾向が見られました。
頬のたるみに関しては、3都市すべてで年齢に応じてスコアが上昇しましたが、統計的に有意な差が確認されたのは、日本人とタイ人女性の30代および50代に限られました。それ以外の組み合わせ(日本人vs中国人、中国人vsタイ人)では有意な差は見られませんでした。

環境や文化的背景が与える影響
気候条件と紫外線曝露の影響
これらの都市の気候データを分析すると、東京と上海は緯度が近く、平均気温も15.9°Cと16.1°Cでほぼ同じです。一方、バンコクは赤道に近く、年間平均気温は28.6°Cとかなり高くなっています。さらに、降水量は東京の1,467 mmに対して、バンコクはわずか529 mmと乾燥しているため、年間を通じて紫外線(UV)曝露量が多いと推察されます。紫外線は皮膚のコラーゲンを分解し、光老化(photoaging)を進行させる主要な外因性因子であるため、気候が老化に及ぼす影響は無視できません。

肌の明るさとシワの見え方
肌の明るさを数値化する尺度であるL*(L-star)値によると、日本人や中国人は比較的明るい肌色を持ち、タイ人女性はより暗い肌色を持つ傾向があります。肌が暗いと、光の反射率が低くなるため、シワやたるみといった凹凸がより目立ちやすくなります。これも、タイ人女性においてシワが深く見える一因と考えられます。

ライフスタイルと表情の使い方の違い
ライフスタイルの観点からは、日本人女性の喫煙率が10〜19%と比較的高い一方で、シワのスコアは最も低いという結果になりました。このことは、喫煙以外の要因、特に日常的な紫外線対策(たとえば日焼け止めの使用)やスキンケアの習慣が、老化に強い影響を及ぼしていることを示唆しています。実際に、日本人女性は日焼け止めやファンデーションの使用頻度が高いとされており、紫外線から肌を保護する行動が広く浸透しています。
また、文化的な表情の違い、特に日常的な笑顔や発話時の口の動きが皮膚の特定部位に与える機械的ストレスも、シワの形成に影響を与える可能性があります。動物実験では、顔の一時的な折り目が紫外線の照射によって恒久的なシワに変わることが確認されており、人間でも似たメカニズムが働いていると考えられます。

高齢者の皮膚老化と生活習慣
地域住民を対象とした客観的イメージ解析
Asakuraら(2009年)は、群馬県高崎市倉渕町という山間地域に住む高齢者(65歳以上)のうち、地域の医療調査に協力可能な802名(男性341名、女性461名)を対象に、皮膚の加齢変化と生活習慣との関係を調査しました。この研究は、主に農村地域で一生を過ごした高齢者を対象にしているため、紫外線曝露などの地域差を最小限に抑えた非常に貴重なデータとなっています。
顔の皮膚状態は、Beauty Imaging System(BIS)というデジタル画像解析装置を用いて測定されました。BISは、高解像度の写真を標準化されたライティング条件下で撮影し、画像解析ソフトを用いて老化の4つの主要な兆候――色素斑(hyperpigmented macules)、毛穴の開き(visible pores)、肌の質感(texture irregularities)、シワ(wrinkles)――の程度を顔の面積比率として定量化します。
解析の結果、男性は女性よりも全般的に色素斑、毛穴、肌のざらつきが目立ちましたが、シワの深さに関しては性別による有意差は認められませんでした。女性では加齢に伴ってすべての皮膚老化指標が増加した一方、男性では特にシワの重症度が年齢とともに顕著に増加しました。

喫煙と紫外線防御の影響
ライフスタイル因子の中で最も強く皮膚状態に影響していたのは、喫煙と紫外線対策でした。男性喫煙者では、非喫煙者に比べて色素斑の面積が平均で+1.34、毛穴が+0.43、肌のざらつきが+0.46ポイント増加していました。女性でも、喫煙者では毛穴(+0.88)と肌質(+0.86)の悪化が確認されました。
一方、日焼け止めやファンデーションなどの光防御製品を日常的に使用している人では、皮膚の老化指標が明らかに良好でした。たとえば、男性では色素斑の面積が−2.14、肌のざらつきが−0.75改善しており、女性では色素斑(−0.52)、毛穴(−0.29)、肌質(−0.22)がそれぞれ改善されていました。
その他の因子――たとえば結婚歴、飲酒、学歴、最長職歴、屋外作業の有無など――は、皮膚の老化指標との関連性が統計的に有意ではありませんでした。これは、屋外作業の自己申告が不正確である可能性や、対象地域が同一地域内で生活していたため環境差が小さかったことなどが影響していると考えられます。
この研究は、皮膚老化が単に加齢の結果ではなく、日常的な生活習慣によって大きく左右されることを示しており、特に喫煙と紫外線対策が皮膚健康の鍵となることを明らかにしました。

双子研究による環境と遺伝の影響分析
一卵性双生児を対象とした肌老化研究
Ichiboriら(2014年)は、皮膚老化がどの程度まで遺伝に左右され、またどの程度まで環境要因に影響されるのかを明らかにするため、日本全国から募集した40〜87歳の一卵性双生児(monozygotic twins)67組を対象に、VISIA® Complexion Analysis Systemを用いた高精度な画像解析を実施しました。一卵性双生児は遺伝情報がほぼ完全に一致しているため、生活習慣の違いによってどれほど肌老化に差が出るかを評価するのに理想的な対象です。
画像解析では、斑点(spots)、シワ(wrinkles)、毛穴(pores)、肌の質感(texture)、紅斑(erythema)の5項目を測定し、顔の左右それぞれのスコアを平均化して比較しました。統計解析にはウィルコクソン符号付き順位検定(Wilcoxon signed-rank test)およびピアソンの相関係数(Pearson’s correlation coefficient)が用いられました。

主な結果と解釈
双子間で最も差が大きかったのは肌の質感(texture)で、年齢が上がるにつれて双子間でのスコア差が有意に広がる傾向が認められました(p = 0.03)。このことは、肌の質感が長年の環境因子(紫外線、スキンケア、生活習慣など)に強く影響されやすいことを意味しています。
さらに、喫煙歴が異なる双子間では、喫煙している方が明らかにシワと肌質のスコアが悪化していました(p = 0.04)。また、日焼け止めやファンデーションを使用していない方が、使用している双子よりもシワのスコアが高い傾向も確認されました(p = 0.03)。
その他の要因(飲酒、ホルモン補充療法、日照曝露歴、結婚歴、BMIなど)は、サンプルサイズの制限もあり、有意な関連性は確認されませんでした。ただし、BMI差が4以上ある双子11組では、BMIが高い方の肌質とシワスコアがやや悪化している傾向が見られ、体重の管理も老化に一定の影響を与える可能性が示唆されました。
この研究により、肌老化は遺伝だけでなく、長年のライフスタイルや外的環境の蓄積に大きく左右されることが明確に示されました。

糖化ストレスと光老化に関する分子メカニズム
糖化反応(Glycation)と皮膚構造の変化
Ichihashiら(2011年)は、老化と密接に関係する「糖化ストレス(glycation stress)」の皮膚への影響に焦点を当てました。糖化とは、糖(特に還元糖;reducing sugars)とタンパク質が酵素を介さずに反応し、最終的に「AGEs(Advanced Glycation End Products;最終糖化産物)」と呼ばれる劣化物質を作る過程を指します。この反応は体内のコラーゲンやエラスチンなどの構造タンパク質にも起こり、皮膚の弾力性や透明感を著しく損ないます。
AGEsは、Nε-(carboxymethyl)lysine(CML)やペントシジン(pentosidine)などを含み、皮膚の中で交差結合を形成し、繊維の硬化や変形を引き起こします。これにより、肌にシワや黄変(肌の黄色味)などが生じるのです。
さらに、AGEsはRAGE(Receptor for Advanced Glycation End Products)という受容体に結合し、炎症を促進するNF-κB経路などの細胞内シグナル伝達を活性化させます。その結果、炎症性サイトカインやMMP(マトリックスメタロプロテイナーゼ)の発現が増加し、コラーゲンの分解が進行します。

紫外線と糖化の相乗効果
UV-BやUV-Aなどの紫外線は、活性酸素種(reactive oxygen species; ROS)を生成し、糖化や炎症をさらに促進します。UV-Bは表皮細胞に炎症性サイトカイン(IL-1α、IL-6、TNFαなど)を誘導し、真皮の線維芽細胞にMMP-1、-3、-9を産生させます。これらはコラーゲンやエラスチンを分解し、しわの形成を加速させます。
AGEの蓄積を非侵襲的に測定する手段として、AGE Reader™などの機器による皮膚の自家蛍光(autofluorescence; AF)測定があります。日本人女性136名を対象にした研究では、AFは年齢とともに有意に上昇しており(r = 0.603, p < 0.001)、老化の信頼できるバイオマーカーと考えられています。

予防と治療の可能性
糖化ストレスに対する予防策には、血糖コントロール、筋肉量の維持(インスリン感受性向上のため)、低GI食品の摂取、砂糖・アルコールの制限、そして毎日の紫外線対策が含まれます。
治療法としては、AGE形成抑制剤(例:アミノグアニジン)、AGE分解促進物質、RAGE阻害剤などが検討されています。また、カモミール、ドクダミ、ブドウ葉などの植物抽出物がAGE生成抑制効果を示しており、今後の研究により臨床応用が期待されています。
RAGE経路の調整も注目されており、細胞膜に結合したRAGEを分解酵素(MMP-9やADAM-10)によって可溶型RAGE(sRAGE)へ変換することで、炎症性シグナルを遮断し、組織へのダメージを抑制する新たなアプローチも提案されています。

総括
これら一連の研究は、皮膚の老化が単に「年を取ること」だけによって引き起こされるのではなく、生活習慣、日常の環境曝露、文化的背景、分子レベルでの反応などが複雑に絡み合って進行することを明らかにしました。紫外線防御や喫煙習慣、スキンケアの有無といった「行動の違い」が、シワやたるみの出方に大きな差を生むことは明確です。
また、糖化ストレスと光老化という分子メカニズムの解明により、老化に対する予防戦略の科学的根拠が強固になりました。今後は、生活習慣の改善とともに、分子標的に基づいた治療や予防製品の開発が求められるでしょう。皆さんにとっても、日々の紫外線対策や食生活の選択が、将来の肌の健康を大きく左右することを、ぜひ覚えておいていただけますと嬉しいです。

キーワード
顔の老化,シワ,たるみ,日本人女性,白人女性,肌の違い,アジア女性,紫外線,生活習慣,スキンケア,糖化ストレス,光老化,肌の弾力,コラーゲン,エラスチン,表情ジワ,文化の違い,日焼け止め,スキンエイジング,肌の構造,肌の科学,肌老化の予防,高校生向け美容,肌の未来,地域差,表皮,真皮,肌の色,肌質,紫外線対策,日常ケア,肌の比較研究,ヒロクリニック

引用文献
- Tsukahara, K., Fujimura, T., Yoshida, Y., Kitahara, T., Hotta, M., Moriwaki, S., Witt, P. S., Simion, F. A., & Takema, Y. (2004). Comparison of age‐related changes in wrinkling and sagging of the skin in Caucasian females and in Japanese females. International Journal of Cosmetic Science, 26(6), 314–314. https://doi.org/10.1111/j.1467-2494.2004.00245_5.x
- Tsukahara, K., Sugata, K., Osanai, O., Ohuchi, A., Miyauchi, Y., Takizawa, M., Hotta, M., & Kitahara, T. (2007). Comparison of age-related changes in facial wrinkles and sagging in the skin of Japanese, Chinese and Thai women. Journal of Dermatological Science, 47(1), 19–28. https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2007.03.007
- Asakura, K., Nishiwaki, Y., Milojevic, A., Michikawa, T., Kikuchi, Y., Nakano, M., Iwasawa, S., Hillebrand, G., Miyamoto, K., Ono, M., Kinjo, Y., Akiba, S., & Takebayashi, T. (2009). Lifestyle factors and visible skin aging in a population of japanese elders. Journal of Epidemiology, 19(5), 251–259. https://doi.org/10.2188/jea.JE20090031
- Ichibori, R., Fujiwara, T., Tanigawa, T., Kanazawa, S., Shingaki, K., Torii, K., Tomita, K., Yano, K., Osaka Twin Research Group, Sakai, Y., & Hosokawa, K. (2014). Objective assessment of facial skin aging and the associated environmental factors in Japanese monozygotic twins. Journal of Cosmetic Dermatology, 13(2), 158–163. https://doi.org/10.1111/jocd.12081
- Ichihashi, M., Yagi, M., Nomoto, K., & Yonei, Y. (2011). Glycation stress and photo-aging in skin. ANTI-AGING MEDICINE, 8(3), 23–29. https://doi.org/10.3793/jaam.8.23