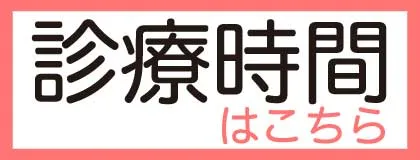陥没乳頭とは何か:定義、頻度、分類
陥没乳頭の定義と基本的な理解
陥没乳頭(英語:Inverted Nipple)は、乳頭が乳房の内側に引き込まれ、外から見たときに突出していない、あるいは全く見えない状態を指します。通常、乳頭は軽く突出しており、授乳時には赤ちゃんが吸いやすいようにさらに前方へ押し出されます。しかし、陥没乳頭ではこの自然な突出が起こらず、見た目にも機能的にもさまざまな問題を生じます。
この状態は、一見して単なる美容上の問題に思われがちですが、実際には授乳機能への影響や衛生管理の難しさ、さらには女性としての自己イメージや自信に関わる深刻な課題を含んでいます。
陥没乳頭の発症頻度と疫学的背景
陥没乳頭は決してまれな状態ではなく、世界中の女性において広く見られます。各国で報告されている頻度は2〜10%と幅広いですが、これは調査対象の年齢層や民族、文化的要因によって異なるためです。日本においても、成人女性の約10%が陥没乳頭であるとされており、女性特有の悩みとして臨床現場でもよく取り上げられます。
1999年に韓国で実施された代表的な研究(Parkら)は、19〜26歳の未婚女性1,625人を対象に身体検査と簡単な面接調査を行い、先天的な陥没乳頭の有病率を3.26%と報告しました。両側の乳頭(合計3,250個)を対象とした分析では、そのうち99個(3.05%)が陥没していたとされています。さらに、症例の86.79%が両側性(両方の乳頭が陥没)、13.21%が片側性であり、片側の場合は左側の発症がやや多いという興味深い傾向も示されました。
このような大規模な調査は、陥没乳頭の全体像を把握し、予防や早期治療の啓発を行う上で非常に重要です。

陥没乳頭の分類:形態と重症度
陥没乳頭は、その形や可逆性(押し出せるかどうか)により、以下のように分類されます。
まず、形態的には大きく2つのタイプに分けられます。
- 臍状型(Umbilicated):指で押したり引いたりすることで、ある程度乳頭が表に出るタイプです。軽度であることが多く、日常生活や授乳に大きな支障を来たすことは少ないとされます。
- 内反型(Invaginated):乳頭が完全に内側に引き込まれ、外からの刺激にも反応しないタイプです。引き出すことが困難であり、重度の分類に該当します。
さらに、臨床的にはHan & Hongによる重症度分類が広く使用されています。これは乳頭の突出のしやすさ、線維化(組織の硬化)や乳管の短縮度に基づき、以下の3段階に分けられます。
- グレードI(Grade I):軽度で、乳頭は指先で簡単に押し出すことができます。
- グレードII(Grade II):中等度で、乳頭を押し出すのにやや力が必要で、内部に線維化が認められます。授乳は困難になる可能性があります。
- グレードIII(Grade III):重度で、乳頭は著しく内反し、乳管の発達不全や短縮も認められ、手術なしでは正常な突出が困難です。
このような分類は、患者一人ひとりに適した治療方針を立てる上で極めて有用です。

陥没乳頭の原因とその影響
発症の仕組みと原因の違い
陥没乳頭の原因は、大きく「先天性(Congenital)」と「後天性(Acquired)」に分けられます。
先天性陥没乳頭は、胎児期の乳頭形成過程における発達不全が主な原因です。たとえば、乳頭の構造を支える間葉組織(Mesenchyme)の増殖が不十分であったり、乳管が十分に伸びず短縮したままであったりすることで、乳頭が正常に外へ突出できなくなります。乳頭の基部に存在する線維束が強く収縮している場合も、突出が妨げられます。
一方、後天性陥没乳頭は、乳がんや乳腺炎(Periductal Mastitis)、手術や外傷、授乳中のトラブル(強い吸引や炎症)などが原因で発症します。こうした後天的な要因によって、乳管や周囲組織に変化が起き、乳頭が内側に引き込まれるようになるのです。

身体的・心理的な影響
陥没乳頭は、見た目の違和感だけでなく、生活の質(Quality of Life)に直接影響を与える状態です。以下のような問題が報告されています。
まず、授乳機能の障害が挙げられます。特にグレードIIやIIIでは、赤ちゃんが乳頭をくわえづらくなることで、母乳がうまく与えられず、母子ともにストレスを抱えることになります。乳管に母乳が残りやすくなり、慢性的な乳腺炎を繰り返すリスクも高まります。
また、内反型では乳頭内部に垢や分泌物がたまりやすく、衛生管理が難しくなるという課題もあります。
さらに、女性の自己肯定感やパートナーとの関係に与える影響も無視できません。性的満足度の低下や、裸になることへの抵抗感を抱くことも多く、患者の心理的ストレスは大きいとされています。
韓国の研究では、陥没乳頭を有していた53名中、手術による修正を望んだのは17%(9名)にとどまりました。これは、審美的・心理的な要因のほか、文化的に身体改変に対する保守的な価値観が影響している可能性が示唆されています。

陥没乳頭の治療選択肢
手術を伴わない治療(非侵襲的療法)
軽度の陥没乳頭(グレードI)においては、まずは手術を行わない保存的治療が選択されることがあります。代表的な方法としては、以下のようなものがあります。
- 吸引装置(Suction Device):市販されているNiplette(ニプレット)などが用いられ、一定期間の使用によって乳頭を突出させることを目指します。
- ピアスなどによる外的固定:乳頭を外部から支えることで、突出を維持しようとする手法です。
- 手による定期的な牽引(Manual Traction):自身で日常的に乳頭を引き出す行為で、一定の効果が期待されることもあります。
ただし、これらの方法は乳頭の状態が軽度である場合に限られ、グレードIIやIIIのような線維化が進んだケースでは効果が限定的です。

陥没乳頭の外科的治療とその手術法
手術による矯正の意義と全体的な治療方針
中等度から重度の陥没乳頭(グレードIIおよびIII)では、手術による矯正が最も効果的かつ再発率の低い治療法とされています。手術の目的は単に乳頭を外へ突出させるだけではなく、将来的な授乳機能の温存や、感覚の保持、術後の見た目の自然さなど、機能性と審美性の両立を図ることにあります。
特に若年女性にとっては、将来の授乳への影響を避けたいという希望が強いため、「乳管温存(Duct-Preserving)」の考え方が重要です。一方で、すでに授乳の予定がない場合や、乳管自体が既に変性している場合には、より確実な矯正を目的として「乳管切断(Duct-Damaging)」による手術も選択肢となります。

手術技術の分類:乳管温存 vs 乳管切断
陥没乳頭の手術は、大きく2つの方針に分類されます。
乳管温存手術(Duct-Preserving Techniques)
この手法では、乳頭の内部にある乳管をできる限り傷つけずに、周囲の線維性拘縮(Fibrous Contraction)を解除することで乳頭を突出させます。たとえば以下のような方法があります。
- 線維性束の鈍的剥離(Blunt Dissection)によって、乳頭基部の拘縮を解除。
- 皮膚を三角形、ひし形、またはダイヤモンド形状に切開し、皮弁(Dermal Flap)を作成して乳頭の支持を強化。
- 乳頭基部に水平マットレス縫合(Horizontal Mattress Sutures)を施し、乳頭の陥没を防止。
- 外部牽引装置(External Distractors)やドーナツ型固定具を用いて、術後の乳頭の突出状態を安定的に保持。
この手法は乳管の損傷リスクが低く、術後の授乳成功率が高いことが報告されています。

乳管切断手術(Duct-Damaging Techniques)
この方法では、乳頭を強く内側へ引き込んでいる乳管そのものを切断し、Z形成術(Z-Plasty)や星型縫合(Star-Shaped Sutures)などを組み合わせて安定した乳頭の突出を目指します。乳管を犠牲にするため、術後の授乳は基本的に不可能になりますが、再発リスクは低く、より確実な矯正が可能です。
この方法は、乳腺炎や腫瘍により乳管が既に機能していない場合や、外観の回復を最優先する患者に対して選択される傾向があります。

実際の臨床例:ヒロクリニックにおける手術
埼玉県川口市にあるヒロクリニックでは、形成外科専門医による保険診療のもと、陥没乳頭の手術が提供されています。手術の流れは以下の通りです。
乳頭をまず牽引して露出させた後、目立ちにくい位置で切開を行います。内部の「陥没癖(Fibrotic Adhesions)」を丁寧に解除し、必要に応じて皮膚の一部から真皮弁(Dermal Flap)を形成して支持力を強化します。その後、乳頭が再度引き込まれないように縫合し、ドーナツ型の固定器具で数日間保護します。
手術後は10日〜2週間で抜糸を行い、時間の経過とともに傷跡は目立たなくなります。

術後の経過と注意事項
ヒロクリニックでは、患者が安心して回復できるように詳細な術後指導を行っています。
- 術後当日は患部を濡らさないように注意し、処方された抗生剤(3日分)と鎮痛剤(3回分)を服用。
- 翌日に受診して創部の状態を確認。問題がなければ翌日からシャワー可。
- 毎晩、入浴後に創部の消毒と軟膏塗布(例:エキザルベ)を行い、ガーゼで保護。
- 抜糸後は1か月程度、茶色い紙テープを貼って創部の保護と瘢痕予防を継続。
高血圧症、抗凝固薬内服中、過去の麻酔トラブルなどがある場合は、必ず事前に医師に申告が必要です。

手術の成績と長期的な予後
再発率と合併症の実態
複数の臨床研究を通じて、陥没乳頭手術の再発率と合併症発生率に関する信頼性の高いデータが蓄積されています。
- Gouldら(2015年):アメリカの診療所で7年間にわたり191乳頭を手術。13%が再発し、合併症(乳頭壊死、感染、治癒遅延など)は全体の15.74%。
- Mangialardiら(2020年):合計3,369乳頭を対象とした大規模レビュー。再発率は全体で3.89%。特に皮弁法および牽引法では1.5%という低再発率を記録。
- Hernandez Yentyら(2016年):文献レビューで、乳管温存法の再発率は0.6%、乳管切断法では9.9%と報告。
このように、乳管を温存するアプローチは、授乳を希望する若年女性にとって極めて有用であると考えられます。

感覚と授乳機能の回復
術後の乳頭の感覚については、大多数の患者で正常な知覚が維持されており、恒久的な感覚低下はごく少数にとどまっています。セメス・ワインスタインモノフィラメントテスト(Semmes-Weinstein Monofilament Test)やブラッシュテストを用いた評価でも、大部分で正常範囲内の反応が確認されています。
授乳に関しても、術後に授乳を試みた患者の96%が成功したとする報告があり、とくに乳管温存法における有効性が支持されています。

患者満足度と今後の研究課題
心理的改善と満足度の傾向
手術後の乳頭の形状、感覚、授乳機能の回復は、患者の身体的な満足だけでなく、心理的・社会的な面にも大きく影響します。多くの女性が術後に「自信が持てるようになった」「パートナーとの関係が良好になった」といったポジティブな感想を述べており、こうした効果は臨床的な指標以上に、生活の質(Quality of Life)向上に直結しています。
しかしながら、患者満足度を客観的に評価するための標準化されたツールは、現在のところ多くの研究で十分に活用されていません。たとえば、乳房手術における患者の満足度や心理的影響を測定するために開発された「BREAST-Q(ブレストキュー)」と呼ばれる評価尺度は、陥没乳頭の研究ではほとんど用いられていないのが現状です。

研究の課題と今後の展望
現在までに報告されている多くの研究は、レトロスペクティブ(後ろ向き)なデザインであり、症例数も限られているほか、術式や評価方法がまちまちであるという問題があります。今後、より信頼性の高い知見を得るためには、以下のような改善が求められます。
まず、症状の重症度を統一的に評価するための分類法として、Han & Hong分類を標準化することが重要です。また、可能であれば客観的な測定機器、たとえば真空マノメーター(Vacuum Manometer)などを用いて乳頭の突出力や内反の程度を数値化する方法も提案されています。
術後評価の標準化も必要です。乳頭の突出量はマイクロメーターなどで測定し、感覚の回復についてはモノフィラメントテスト、ブラッシュテスト、あるいはPressure-Specified Sensory Device(圧覚特異的感覚測定装置)を用いることで、定量的なデータの蓄積が可能になります。

加えて、術後の瘢痕(きずあと)の目立ち具合や、患者自身の満足度を評価するために、Patient and Observer Scar Assessment Scale(POSAS)や視覚アナログスケール(Visual Analog Scale:VAS)といった尺度の導入が期待されます。
さらに、術後6か月以上の長期フォローアップを標準とし、治療前後の比較ができるようにすることも、今後の臨床研究の質を高めるうえで不可欠です。患者背景(年齢、授乳希望の有無、既往歴など)を詳細に記録し、再発率、感覚回復、審美的満足度といった複数のアウトカムを包括的に評価する枠組みが求められています。

結論:個別性を尊重した安全で効果的な治療選択を
陥没乳頭は、外見上の問題にとどまらず、授乳や性感、衛生面、そして心理的な側面にまで影響する複雑な状態です。特に若年女性や将来妊娠・出産を希望する方にとっては、授乳機能を温存しながら自然な乳頭形状を取り戻すことが治療の大きな目標となります。
現時点で最も有効かつ再発率が低いとされるのは、乳管を温存しながら線維性の癒着を解除する乳管温存手術(Duct-Preserving Techniques)です。これにより、美容的な満足度だけでなく、授乳機能や乳頭の感覚といった生理的な機能の維持が可能になります。
一方で、乳管がすでに損傷している場合や、美容的改善を最優先したい場合には、乳管切断を伴う方法(Duct-Damaging Techniques)も有効な選択肢となり得ます。重要なのは、患者一人ひとりの背景、希望、生活スタイルを十分に考慮したうえで、最適な治療方針を立てることです。

今後は、手術技術のさらなる洗練に加えて、術後評価の標準化、長期的なフォローアップの体制整備、そして医療従事者と患者の間の丁寧なコミュニケーションがますます重要になります。治療法の進歩とともに、患者が納得し、安心して治療に臨める環境づくりこそが、最も求められる未来への課題といえるでしょう。

キーワード
陥没乳頭,乳頭の悩み,乳頭がへこんでいる,乳頭が出ない,先天性陥没乳頭,乳管温存,乳頭の手術,授乳トラブル,乳頭の治療法,思春期の体,乳頭の病気,乳頭の発育,陥没乳頭とは,乳頭の構造,乳管,形成外科,女性の体,乳頭の形,乳頭の異常,乳頭の症状,母乳育児,乳頭の悩み対処法

引用文献
- 川口市の形成外科・皮膚科は川口駅から徒歩3分のヒロクリニック|皮膚科・形成外科の専門治療ならヒロクリニック. (2021年7月21日). Retrieved 28 March 2025, from https://www.hiro-clinic.or.jp/dermatology/course/invertednipple/
- Park, H., Yoon, C. & Kim, H. The Prevalence of Congenital Inverted Nipple. Aesth. Plast. Surg. 23, 144–146 (1999). https://doi.org/10.1007/s002669900258
- Gould, D. J., Nadeau, M. H., Macias, L. H., & Stevens, W. G. (2015). Inverted nipple repair revisited: A 7-year experience. Aesthetic Surgery Journal, 35(2), 156–164. https://doi.org/10.1093/asj/sju113
- Mangialardi, M. L., Baldelli, I., Salgarello, M., & Raposio, E. (2020). Surgical correction of inverted nipples. Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, 8(7), e2971. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000002971