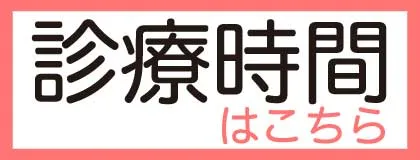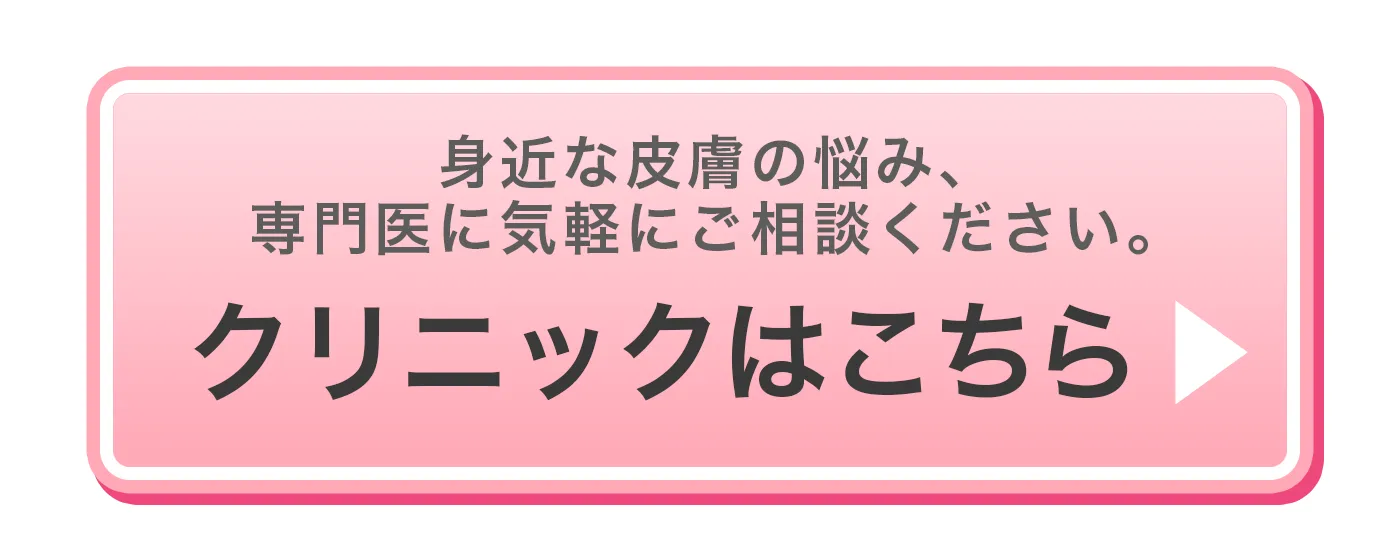はじめに
表皮嚢腫(epidermoid cysts、別名:粉瘤〔ふんりゅう〕)は、皮膚の下にできる良性(=がんではない)の嚢(ふくろ)のような腫瘤(しゅりゅう)です。まるで「おでき」や「にきび」のように見えることもありますが、原因も構造も異なります。このような嚢腫は、毛の根元にある「毛包(hair follicle)」という部分から発生すると考えられており、皮膚科や形成外科で非常に一般的に扱われています。
基本的には痛みもなく、放置していてもすぐに命に関わるようなことはありません。しかし、長期間放っておくと次第に大きくなったり、炎症や感染を起こしたりすることがあり、その場合には痛みや腫れ、膿の排出などの症状が現れます。特に顔など目立つ部位にできた場合、美容的な観点から手術によって取り除くことが望まれることもあります。

表皮嚢腫の特徴や診断方法、治療法だけでなく、顔にできた場合の美容的な手術アプローチ、そして思春期の若者における美容手術の社会的背景とリスクまで、幅広く丁寧に解説していきます。
表皮嚢腫とは何か:その特徴と診断
発生のしくみと組織の構造
表皮嚢腫は、毛包のうち皮膚の表面に近い「漏斗部(infundibular portion)」と呼ばれる部位から発生します。この部分は皮脂(=皮膚を守る油分)を分泌する管ともつながっており、皮脂の出口が詰まったり、皮膚の内側に袋ができてしまうことで嚢腫が形成されます。
顕微鏡で見ると、嚢腫の壁は「扁平上皮(stratified squamous epithelium)」という皮膚の表面に似た細胞で構成されており、その内側には「ケラトヒアリン顆粒(keratohyaline granules)」という粒子が含まれています。これらの特徴は、毛包の上部構造に特有のもので、診断の際の手がかりとなります。

見た目と症状:なぜ見逃されやすいか
通常、表皮嚢腫はゆっくりと成長し、皮膚の下にしこりのように現れます。痛みはほとんどありませんが、炎症や感染が起こると、赤く腫れたり、膿が出てきたりして、強い痛みを伴うこともあります。
多くの場合、顔、背中、胸など皮脂腺が多い場所に発生します。特に特徴的なのは、中心に小さな穴(punctum:中心小孔)が開いていることがあり、これが診断の決め手になることもあります。膿や皮脂がこの穴から出てくることもあります。
そのまま放置すると、しこりは親指大くらいまで成長することもあり、極端な例ではダチョウの卵ほどの大きさにまでなることも報告されています。

画像検査と最終診断
見た目や触った感触である程度は診断できますが、腫瘍との区別が必要な場合には画像検査が有効です。超音波検査(ultrasound)は、皮膚の下にある構造をリアルタイムで観察できる簡便な方法です。さらに精密な検査が必要な場合は、CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)を用いることもあります。
最終的な確定診断には、摘出した嚢腫を病理検査(biopsy)で調べ、内部の構造や内容物を確認します。

日本および韓国における疫学データと治療傾向
年齢と性別による発症傾向
韓国のある病院で行われた20年間の大規模な調査(Kimら, 2020)によると、398名の患者から432個の表皮嚢腫が外科的に摘出され、詳細な分析が行われました。年齢層は6歳から96歳までにわたり、特に40代・50代が多く、それぞれ全体の17.6%を占めました。続いて多かったのは20代(16.8%)、30代(16.1%)、60代(14.6%)でした。
性別では男性が59.5%、女性が40.5%と、男性にやや多い傾向がありましたが、過去の研究(1.8:1~4.6:1)に比べると男女差は縮まってきています。これは、美容への関心の高まりや、女性の社会的な活動機会の増加、保険制度の普及などによって、女性の受診率が上がっていることが影響していると考えられます。

発生しやすい部位:なぜ顔が多いのか
最も多く表皮嚢腫が見つかった部位は顔で、全体の65.0%を占めました。顔の中では頬(20.8%)が最多で、次いで耳の周囲(12.7%)、目の周囲(10.9%)となっており、人目に触れやすい部位に多いことがわかります。これは、皮脂腺が発達している場所にできやすいという生理的な理由だけでなく、顔の見た目に対する意識の高さも反映していると考えられます。

合併症や基礎疾患との関係
対象となった患者のうち24.6%は、高血圧、糖尿病、高脂血症などの基礎疾患を有していましたが、これらの疾患と嚢腫の直接的な因果関係は認められませんでした。

美容的観点からの手術アプローチ:顔にできた場合の対処法
なぜ顔の嚢腫には特別な配慮が必要なのか
顔は他人の視線を最も集める部位であり、見た目に大きく影響するため、手術によってできる傷跡(瘢痕)が患者の心理や日常生活に与える影響も大きくなります。特に若年層では、傷跡による自己評価の低下や対人関係への影響が懸念されるため、できる限り目立たない方法での摘出が求められます。

美容外科的アプローチの工夫
アメリカの研究(Cilloら, 2006)では、顔面の嚢腫や脂肪腫(lipomas)をできるだけ目立たない傷跡で切除するために、以下のような工夫が紹介されています。
例えば、通常であれば嚢腫の真上に直線的な切開を加えて取り除きますが、顔の場合には髪の毛の生え際(こめかみや耳の後ろ)やあごの下、まぶたのすぐ下など、自然な陰影に隠れる部位からアプローチして、皮膚を下から剥がしながら嚢腫にアクセスします。こうした方法を「リモートアクセス(remote access)」または「隠れた切開(concealed incision)」と呼びます。
この際、局所麻酔だけでなく、「チュメセント麻酔(tumescent anesthesia)」という特殊な麻酔液を皮膚の下に大量に注入し、出血を抑えながら皮膚を柔らかくし、剥離しやすくします。摘出後は、層ごとに丁寧に縫合し、場合によってはドレーン(drain:体液の排出管)を挿入して、術後の腫れや内出血を防ぎます。

代表的な症例と結果
実際の症例では、頬やあご下、中顔面(目と口の間)などにできた嚢腫や脂肪腫を、Sリフト(S-lift:部分的なフェイスリフト)や下眼瞼切開(lower eyelid blepharoplasty)などの技法を併用して、ほとんど目立たない傷で除去しています。
術後にわずかな腫れや脂肪の減少によるくぼみ(陥没)を残すこともありますが、ヒアルロン酸(hyaluronic acid)などの注入材で補正することで、良好な結果が得られたと報告されています。

思春期における美容医療の広がりとそのリスク
なぜ10代で美容手術を希望する若者が増えているのか
近年、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、若者たちは他人と自分の外見を比較する機会が急増しました。InstagramやTikTokなどでは、「加工された理想的な顔や体」が日常的に流れ、それに影響されて「自分も変わりたい」と感じる中高生が増えています。さらに、いじめや外見に対するからかい、就職や進学などのタイミングで「もっと見た目を良くしたい」と強く願うようになる傾向もあります。
インドでの研究(Khunger & Pant, 2021)では、13歳から19歳の間に美容処置を希望する青少年が増加しており、特にニキビやニキビ跡、過剰な体毛(多毛症)、刺青の除去、乳房の左右差などの悩みが多いと報告されています。

思春期の美容手術に伴う医学的・心理的・法的な配慮
思春期は身体的・精神的に発達の途中であり、美容手術を受けるかどうかの判断は非常に慎重に行う必要があります。
まず、身体がまだ成長しているため、13歳の時点では気になっていた鼻や乳房の形も、18歳には自然に整っていることが少なくありません。したがって、早い段階での手術は「必要ない場合が多い」とされています。
また、見た目に強いこだわりを持ち、「ここを変えれば人生が変わる」と思い込んでいる場合、それが「身体醜形障害(Body Dysmorphic Disorder:BDD)」という精神的な疾患である可能性もあります。この疾患は、美容手術を何度受けても満足できず、場合によっては深刻なうつ症状や自殺念慮に発展することもあるため、精神科の評価が不可欠です。

安全な手術のために必要なステップ
ガイドラインでは、10代の患者に対して美容手術をすぐに行うのではなく、「クーリングオフ期間(cooling-off period)」として3ヶ月ほど時間を置き、その間にカウンセリングを重ねることが推奨されています。また、必ず保護者の同席のもと、手術のリスク、結果の限界、術後ケアの必要性などを丁寧に説明する必要があります。
手術が必要と判断された場合でも、非手術的な方法(薬やスキンケア)から試すことが優先されるべきです。たとえば、レーザー脱毛(laser hair removal)は初潮から2年以上経過していないと効果が安定せず、化学ピーリングやタトゥー除去も炎症や色素沈着のリスクがあるため、慎重な判断が必要です。

結論
表皮嚢腫は一見無害に見えるものの、放置すると大きくなったり、炎症や感染を起こすリスクがあります。特に顔など目立つ部位にできた場合、美容的な観点から適切な手術手技による摘出が重要です。
また、思春期における美容医療の需要は今後も増えると予想されますが、それに応じて医学的・倫理的・心理的な配慮も一層求められます。医師や保護者は、若者の心と体の成長を理解し、見た目の悩みに寄り添いながらも、不必要な処置は避け、必要な支援と時間を提供する姿勢が大切です。
今後は、青少年を対象とした安全で適切な美容医療ガイドラインの整備と、医療従事者の教育体制の充実が期待されます。美容医療は「変わること」だけでなく、「自分を受け入れる力」を育む機会にもなり得るのです。

キーワード
粉瘤, 表皮嚢腫, ふんりゅう, ニキビとの違い, 思春期の肌トラブル, 顔のしこり, 粉瘤 手術, 粉瘤 治療, 顔 粉瘤 美容外科, 顔 傷跡 残さない, 下眼瞼切開, Sリフト, 身体醜形障害, BDD, 青春期 美容整形, 思春期 美容医療, 高校生 美容, SNSと容姿, ボディイメージ, クーリングオフ期間, 精神的サポート, 顔 粉瘤 痛い, 膿 出てきた, ヒロクリニック, 埼玉 形成外科, 川口市 皮膚科

引用文献
- 川口市の形成外科・皮膚科は川口駅から徒歩3分のヒロクリニック|皮膚科・形成外科の専門治療ならヒロクリニック. (2021年7月21日). Retrieved 28 March 2025, from https://www.hiro-clinic.or.jp/dermatology/course/powder-lump/
- Kim, C. S., Na, Y. C., Yun, C. S., Huh, W. H., & Lim, B. R. (2020). Epidermoid cyst: A single-center review of 432 cases. Archives of craniofacial surgery, 21(3), 171–175. https://doi.org/10.7181/acfs.2020.00248
- Cillo, J. E., Caloss, R., & Wendelken, J. A. (2006). Excision of subcutaneous facial cysts and lipomas using cosmetic approaches. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 64(11), 1603–1616. https://doi.org/10.1016/j.joms.2005.11.093
- Khunger, N., & Pant, H. (2021). Cosmetic procedures in adolescents: What’s safe and what can wait. Indian Journal of Paediatric Dermatology, 22(1), 12. https://doi.org/10.4103/ijpd.IJPD_53_20